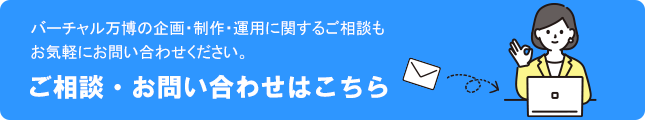迫る大阪・関西万博「バーチャル万博」に熱い視線

2025年4月13日の開催を控え、日増しに注目度が高まる大阪・関西万博(2025日本国際博覧会)。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、多様な技術が展示される同万博ですが、「バーチャル万博」を標榜するなど、XRも最重要技術の一つとなっています。今回は万博におけるXR活用の構想とその意義について、公式資料などから探ります。
未来社会に向けたXRの実証実験

大阪・関西万博は「未来社会の実験場」をコンセプトに掲げるように、先端医療や空飛ぶ車(eVTOL)、自動運転、再生可能エネルギー、DXなど様々な社会課題に対応するイノベーションを会場内外で実装する社会実験の場であり、その際にXRは重要なキー技術となります。
内閣官房が公表する「2025年大阪・関西万博アクションプラン」によると、同万博ではARやVR等を活用してバーチャル会場プラットフォームを構築、会場や各パビリオン外観の3DCGでの再現等により「多くの方々がバーチャル参加を体験できるインクルーシブな万博」を実現するとしています。
サイバー空間に拡張する展示場
個々の展示内容についてはあくまで計画段階ですが「アクションプラン」の中で挙げられる計画の中には、XRを駆使した興味深いものが多数あります。
例えば、国土交通省が中心に計画するのが、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)や空間移動の振動や重力を体感できるVRチェアによる、大阪・関西万博周辺エリアのバーチャルな走行体験。同省が主導する日本全国の3D都市オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」を用い、現実世界とバーチャル世界を行き来する走行体験が提供されるとしています。
アクションプランではその他にも多様なバーチャル展示・催事、バーチャルトリップなどの計画例が紹介されています。万博会場の大阪・夢洲から、展示場がシームレスにサイバー空間へ拡張されていくような、まさに「未来社会」を予感させる展示が期待されます。
二つの空間が並存・融合

次に、大阪・関西万博の主催主体である、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が発表した「バーチャル万博全体概要」を参照します。
同資料では万博会場を「リアル(フィジカル)空間」と「オンライン(バーチャル)空間」の2つに分け、双方でXR技術を活用するイメージを描いています。
その実現のために必須となるのが、万博の出展者がXRコンテンツを制作できる環境です。同協会は概要の中で、出展者に対しバーチャルパビリオンの内観や展示物等の制作・運営を行うための3D出展コンテンツ制作ツールを提供するといったバックアップ体制についても解説しています。
注目の企業パビリオンは?
万博の大きな見どころの一つに、企業・団体による趣向を凝らした民間パビリオンがあります。大阪万博では13の企業・団体のパビリオンが設置されますが、ここでも各社によりXRを駆使した展示が行われます。
例えば「Natural 生命とITの<あいだ>」をテーマにしたパビリオンで「リアル・バーチャルで万博を訪れる皆さまにワクワクするような未来、社会課題への気づきを感じていただくこと」を目指すNTT、α世代の子供たちに「ノモの国」と名づけた世界での非日常な冒険体験を提供するパナソニック ホールディングス、人気アニメをモチーフとした「ガンダムパビリオン」で「リアルとバーチャルの連動した未来体験」を提供する、バンダイナムコホールディングスなどが挙げられます。
参加各社が、統一テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に合わせて世界に発信するメッセージとともに、バーチャル万博の実現に向けたXRへのアプローチもまた、企業パビリオンの大きな注目点と言えるでしょう。
XRで「万博新時代」へ
1851年、イギリス・ロンドンでの初開催から、万博は世界各国の文化や最先端の科学技術を知る場として注目されてきました。時代を経て万博の意義や役割も変化する中、大阪・関西万博の「バーチャル万博」の挑戦は、新たな画期となる可能性を感じさせてくれます。多様な参加者により、どのような「未来社会」が描き出されるのか、その手段としてXRがいかに取り入れられることになるのか、興味は尽きません。

 もくじ
もくじ