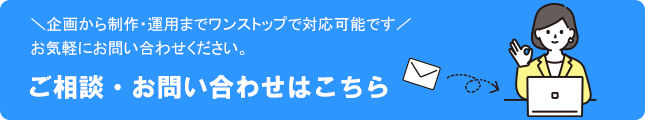ビジネスにおけるXRの可能性:実際の導入事例から学ぶ

XR(Extended Reality)とは、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、複合現実(MR)の総称を表します。まだ世間に広く浸透したとは言いにくいこれらの技術ですが、ビジネスの現場にどのような影響を与えることができるかについて、様々な観点から注目されています。
従来の業務フローや体験を変革する力を持つXR技術は、多くの企業にとって大きな可能性を秘めています。現状、どういった業務領域に導入すれば効果的なのかという点について、様々な企業が検討と検証を行っている段階です。
今回は主にBtoCの領域で、XRがビジネスに与える影響について、バーチャルショールームやバーチャルイベントの実例を交えて解説します。
バーチャルショールームが生む新たな顧客体験

バーチャルショールームのメリット
バーチャルショールームは、物理的なショールームの概念をデジタル空間に移し、顧客が自宅やオフィスから商品を体験できる仕組みです。これにより、実際のショールームに訪れることなく商品の詳細を確認することができ、商談をよりスムーズに進めることが可能です。
インテリア業界や不動産業界、自動車業界では、バーチャルショールームの活用が進んでいます。例えば家具をオンラインで購入する際に、AR技術を使って、実際の部屋に家具を配置したシミュレーションを行う試みがあります。自分の部屋に置いた時のサイズ感などを確かめてみることで、購入前後のイメージのギャップを解消できるなどの利点があります。
また、注文住宅や分譲マンションの販売の際にもVRを利用した打ち合わせが増えてきています。従来の平面図面や、壁紙サンプルなどだけを使った説明の場合、専門家ではない顧客には実際の建築後のイメージを明確に想像することが難しい場合も多く、完成後の物件を見た際に、建具のサイズ感や生活導線などがイメージと違っていた、ということもありました。
そこで、物件の完成形を3Dモデルで再現し、VR空間上で確認できるようにすることで、明確に完成像を理解できるようになり、担当者との打ち合わせについても具体的かつスムーズに要望を出すことで、完成後のトラブルを避けられるようになってきました。
リアルのサービスと比較して
バーチャルショールームは特に高額商品や空間的な広がりが必要、つまりは物理的に大きな商材に向いています。家具、自動車、不動産など、物理的なサイズ感やデザインを確認したい商品はバーチャルショールームと相性が良いと言えるでしょう。
例えば、自動車業界では、顧客が360度の車内外を自由に見回せることに加えて、カラーや内装のカスタマイズをリアルタイムでシミュレーションできるため、販売促進に役立っています。
一方で、質感が重要な商品を選ぶのには向いていないでしょう。例えば洋服のコーディネートのお試しARは多く活用事例がありますが、着心地、質感を確認したいとなるとバーチャル体験では期待を満たせない場合があります。
どうしてもバーチャル空間では商品に直接触れられない以上、触角を伴う商品は引き続き物理的なショールームが重要になるでしょう。
バーチャルイベントの効率的な営業ツールとしての活用

バーチャルイベントもまた、XR技術の普及によって革新が期待されます。
コロナ禍においては、従来の物理的な展示会やイベントが一時的に開催困難となる中、企業は代替手段としてバーチャルイベントの開催を積極的に模索しました。また、イベントの開催制限などがなくなった後も、バーチャルイベントは様々なメリットがあるため検討・実施されています。
バーチャルイベントのメリット
バーチャルイベントの大きな利点は「参加しやすさ」です。従来のイベントでは、参加者が会場に足を運ぶ必要があり、移動や宿泊の手間が生じていましたが、バーチャルイベントではこのような物理的な制約がなくなり、業務負荷の軽減につながります。特に、時間や場所に囚われずに参加できることは、忙しいビジネスパーソンにとって大きなメリットと言えます。
リアルでセミナーや式典を行う場合は、開催する度に会場費や設営費、また会場手配にかかる人件費などのコストがかかることになります。しかし、バーチャル上で行う場合は、一度会場を制作してしまえば、以降のイベントでも繰り返し利用することができます。さらには、制作した会場のカスタマイズも自由に行えるため、それぞれのイベントの雰囲気に合った空間を再現することも可能でしょう。
加えて、バーチャルイベントは基本的に人数を制限する必要がなく、場所を選ばないこともあり、より多くの参加者を募ることが可能です。リアルの時とは異なり、チャット機能などを利用することで、気軽にコミュニケーションを取ることができるため、参加者にとって発言しやすい環境を提供することになります。そのほかにも、アンケート等を通し、参加者の情報を容易に収集することができるため、イベント開催後のフォローに繋げることも可能です。
リアルのイベントと比較して
一般的な説明会や展示会などの場合は、前述したメリットの恩恵を最大限に受けることが可能でしょう。ただし、実際のイベントで体感するような臨場感を味わう場合は、現状リアルのほうが向いています。そのため、イベントの内容によってはバーチャルとの相性が悪く、互いの持ち味が十分に発揮されない場合があります。
さらに、バーチャルイベントの導入するにあたって、スタッフに新しい技術への習熟が求められます。ある事例では、アバター操作に不慣れなためにイベント中の接客が滞るケースも見られました。商品をどう効果的に見せるか、バーチャル空間での接客方法についても検討する必要があるかもしれません。
そして、リアルイベントに比べて参加者のエンゲージメント(興味関心や参加意欲)を維持する工夫も必要になってきます。自宅などから参加の場合、周りの目がないことから緊張感がなくなり、イベントに対する集中力が削がれやすくなる場合があります。また、いつでもどこでも参加しやすいという半面、いつでもイベントから容易に離脱できるという側面もあるため、どのように興味を引き続けるかの工夫が、リアルのイベント以上に求められるでしょう。
まとめ:ビジネスでのXR活用の未来
XR技術は企業に革新的な営業手法を提供する可能性を秘めています。
従来のビジネスプロセスや顧客との接点のあり方が変わり、特にデジタル領域における顧客体験が大きく向上するでしょう。バーチャルイベントでは、物理的な制約に囚われない演出を行うこともできます。
もちろん、現在のXR技術で再現できることは限られているため、リアルと併用しながら利用していくのが基本となるでしょう。そこで、互いのメリットを活かす方法を模索していくことで、今以上の効果的なサービス提供を促進し、開拓途中であるXRビジネスの競争優位を手に入れられるチャンスに繋がっていきます。
現状、多くの企業が様々な形でXRの活用を実験・実証している段階ですが、技術の進化とともに、XRがビジネスの主流となる日もそう遠くないかもしれません。来たる日に備えて情報収集を行い、予め行動しておくことが、新時代の波に乗る鍵となるでしょう。
最後に
しかし、今まで全く触れてこなかった分野や技術について学んでいくのは、少々ハードルが高いと感じるでしょう。加えて、これから進化し続けていく時代の流れについていくには、迅速な対応が必要不可欠になります。そのため、物事を一から始めていくよりかは、企業間で互いに協力していくことで、効率よく適応することができるでしょう。
弊社は企画段階のご相談にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 もくじ
もくじ